INTRODUCTION学生紹介
STUDENT INTRODUCTION
海洋管理政策学専攻
長塚 美月 NAGATSUKA MITSUKI
専攻分野:海洋利用管理学
指導教員:北門 利英
メンター:関口 良行、横田 賢史

増え続ける人口・需要に魚が枯渇しないよう、漁獲量をコントロール。将来は海外で働きたい
適切な漁獲量はどのくらい? 数式を使いシミュレーションして説明
カンボジアにあるトンレサップ湖に棲む淡水魚資源の解析が私の研究です。漁業者や漁獲量、日付などのデータをもとに、どのような要因が漁獲量に影響するかを明らかにし、実漁業データを正解データとしてモデル構築を行うことで、現状の資源状態の把握を行っております。
学部時代では、シンブルな説明変数を用い、魚種ごとの解析行っていましたが、を、修士課程では湖に生息する多くの魚種を考慮し、生態系モデリングへと発展させていきたいと考えております。
カンボジアの湖を研究対象としたのは、大学時代にカンボジアにある養殖場にインターンシップに行ったのがきっかけです。海水魚が中心の日本とは違い、川や湖の淡水魚資源が豊富な点が面白く感じました。また、教授からトンレサップ湖のデータを提供していただけるという偶然が重なり、海外の湖の魚について研究することになりました。
東南アジアは人口が増加しており、これから経済成長していくエリア。魚の需要もあります。その一方、魚を採りすぎると資源が枯渇する恐れが。その漁獲量を感覚的でなく、数式を使いモデルを通じて示せるようにしたいです。「この量は採りすぎ、何トンまでなら取っていい」というように、ルールの規制をする中で生きてくる研究になるでしょう。ルールがあることで漁業者も安定した収入を確保でき、魚を安定して供給できる。そういう環境づくりに役立つ研究になるはずです。
この研究は、自分の手を動かし数式を使って、資源としての魚の減少をシミュレーションしたうえで説明できます。そこが面白いですね。
「授業についていけるだろうか?」不安を解決してくれたのは、卓越大学院プログラムに参加していた先輩
身近にプログラム生の先輩がおり、その方の研究を見ているうちに、AIの可能性の大きさや研究への有用性を感じ、自分も参加したいと思いました。
その一方、不安もありました。自分の中でAIの定義がわからず「結局AIってなんだろう」と感じていましたし、卓越大学院プログラムで学ぶ内容は研究に生かせると思う反面、自分にできるだろうか、授業についていけるだろうかと悩んでいました。結果的に応募し今に至るのですが、プログラムに応募する前にプログラム生の先輩に内容や難易度を聞くことができたのが大きかったです。私が学部生の頃から研究でプログラムを書いているのなら、それなら問題ないだろうと。それがきっかけで「卓越大学院プログラムに参加しよう」と決心しました。
自分でプログラムを組むことはありましたが、機械学習を学ぶのは初めて。授業を聞いてすぐに理解できるわけではなく復習が必須ですが、わかると楽しいし面白いです。卓越大学院プログラムでの授業はもちろん、大学院では自分の専門だけを学べるので、学部時代よりも楽しさと達成感、モチベーションの度合いが違います。
自分の研究と卓越大学院の授業が重なる部分もあるので、研究と勉強を平行して行っています。卓越大学院プログラムで学ぶ内容は、いずれにせよ今後の研究のために知っておいたほうがいい内容。1日5時間くらいは研究を交えつつ、卓越大学院プログラムの勉強をしています。
AIを学ぶ環境が整い、勉学に対するモチベーションが高まった
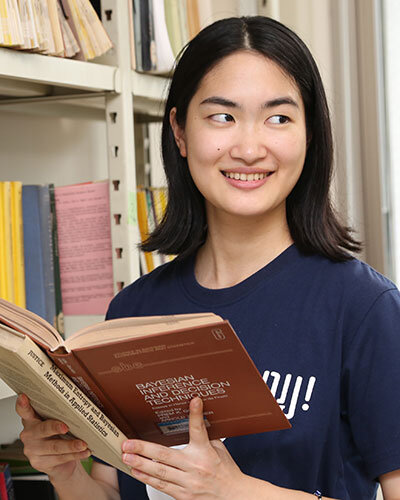 卓越大学院プログラムに参加することで、AIに関して勉強することのできる環境が整ったことが大きなメリットです。
卓越大学院プログラムに参加することで、AIに関して勉強することのできる環境が整ったことが大きなメリットです。
日々使用する多くのサービスがその背景でAIを使用しており、消費者としては便利さという恩恵を受けつつ、実際その仕組みについての知識はあやふやなままです。今後もますますと発展していく分野だと思いますが、一方で、高度な技術だけが独り歩きし、消費者として何も考えずにAIに踊らされることに疑問を感じてもいます。
AIの便利さとその代償を理論的に理解したいという点で、前々から興味はあったものの、分野柄、難易度が高いため、他の勉強と同時進行で行うことが難しいのではと考え、なかなか手を出せずにいました。しかし、現プログラムでは、ほぼ全ての履修授業がAIに特化した内容となっており、また同プログラムの履修生と話す機会が度々あり、腰を据えて学ぼうというモチベーションがとても高まりました。
気分転換を挟みながら研究を行う
ラッシュを避けるため登下校を通勤時間とずらしたいことと、夜のほうが集中できることから、私の研究スタートは午後からです。朝起きたら運動して1日のスタートを切り、お昼頃に登校。日によりますが、リフレッシュを挟みながら夜頃まで勉強と研究をしています。往復の通学時間には読書をすることもよくあります。また、気分転換は人との会話。違う研究室や大学とは関わりのない友達と話すのが私のリフレッシュ方法。自分の研究から離れ、異なる環境の人たちと会話することで気持ちが切り替わります。長期的に良い質の勉強を続けるためには、心身ともに健康なのが一番大切なことと思います。
卓越大学院プログラムと大学で学んだ知識を持って、将来は海外で働きたいです。今学んでいるプログラミングや水産の知識全部が仕事に生かせるかはわかりませんが、学んだことを応用していければと思います。

